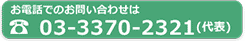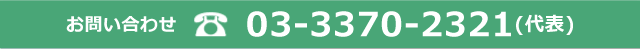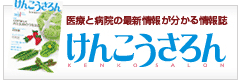診療協力部には、薬剤科と診療技術科の2つの科があり、多種多様な国家資格を持つプロの技師たちが、医師や看護師とともにチーム医療の一員として診療をサポートしています。
外来患者さんが、安心・安全に注射薬の投与を受けられるように調剤を行っています。 内服薬については院外処方せんを発行して医薬分業を積極的に推進しています。
病院内で使用する医薬品の購入と保管、各部署への供給を行っています。
薬に関する情報を収集し、医師や看護師に情報提供しています。
市販されていない薬の調製を行います。
診療技術科は、臨床検査(生理検査、病理検査、検体検査)、放射線、リハビリテーション、眼科検査、臨床工学、栄養管理など、8つの部門から成り立っています。
職種に応じた国家資格を持つプロ技師たちが、医師、看護師、事務など他部門と密にコミュニケーションを図りながら、各診療科の診断や治療に必要な検査や訓練ならびに医療機器の管理点検など多彩な業務に携わっているのが当科の特徴です。
患者さんが1日も早く笑顔を取り戻せるように、「正確で迅速な検査と結果を臨床医に報告する」「患者さんと共に身体回復を目的とした訓練を行う」など、信頼される診療技術科を目指して日々努力しています。
臨床検査では、生理検査、病理検査、検体検査の3つの部門と外来採血において、国家資格を有した【臨床検査技師】が担当しています。
超音波検査は部位によって使用する音波の周波数が異なり、身体にあてる機械(プローブ)を使い分けて心臓、腹部、表在(乳腺・甲状腺・リンパ節など)泌尿器、頸動脈、血管などの様々な領域を検査しています。また、【超音波検査士】の資格を保有した臨床検査技師が担当しています。
他に、心電図検査、ホルター心電図検査、血圧脈波検査などの循環器機能検査、呼吸機能検査、脳波検査、重心動揺検査、聴力検査などを行っています。
手術や内視鏡などで摘出された組織を病理医が顕微鏡を見て診断できるように標本を作製します。また、【細胞検査士】の資格を保有した臨床検査技師が、婦人科や呼吸器、乳腺などから採取した細胞を対象にして主に悪性細胞があるかどうかの判定を行います。
採取された血液中の赤血球や白血球・血小板の数、血清中の酵素や脂質、腫瘍マーカーなどの検査、肝炎ウィルスなどの感染症検査、血液型や輸血に関する検査、尿を材料とした糖や蛋白の検査、便の潜血検査などを行います。
診療放射線技師が、様々な放射線診断機器を操作し、診断・治療に最適な画像を提供しています。
デジタルX線画像診断システム(FPDシステム)を使用し、より高精度で診断に有効な撮影に取り組んでいます。
2023年導入の高性能FPDシステムを使用しています。また、日本乳がん健診精度管理中央機構の施設認定を取得しており、高い品質管理を行っています。また、認定技師の資格を持つ技師によって撮影技術の向上を図っています。
2021年2月に80列(160スライス)CTを導入しました。人工知能の技術を使用して画像を作成し、高画質・被ばく低減・造影剤減量を実現、より高精度に病気の診断に役立つことをめざしています。さらに、心臓の血管(冠動脈)など、最新の画像処理装置を使用して3D画像を作成し、診断に役立てています。
多目的デジタルX線透視装置にて、胃・大腸のバリウム検査などを行っています。
腰椎及び大腿骨を、ガイドラインで推奨された、精度が高いDXA法にて、骨粗鬆症の診断・治療に役立てています。
【言語聴覚士】が機能回復を目標にリハビリテーションを展開しています。
当部門は耳鼻咽喉科に付属しており、医師の指示のもと外来にて、声の問題(声がれ、声の出しにくさ等)をもつ患者さんの音声リハビリテーションを中心に実施しています。
当部門は、【視能訓練士】が医師の指示のもと眼科一般検査を行っています。
患者さんのQOL(クオリティ・オブ・ライフ)を守るべく、各人に適した眼鏡作成や緑内障の早期発見が可能な光干渉断層計(OCT)検査などを行っています。
*コンタクトレンズ処方は行っておりません。
臨床工学部門は、臨床業務と医療機器管理業務の2つに分かれており、【臨床工学士】が担当しています。
臨床業務は、血液浄化療法、腹水濃縮再生静注法(CART)、ペースメーカー関連業務等があります。
医療機器管理業務は、院内で使用している人工呼吸器、輸液・シリンジポンプなどの医療機器整備点検等を行っています。
管理栄養士が外来の患者さまへ、各疾患に応じた食事療法の実践について栄養食事指導を行っています。
◇ 患者さま一人ひとりに合わせ、分かりやすく行います。
◇ 身体測定では体組成計(InBody270)を活用し、筋肉・体脂肪を測定します。
◇ 栄養食事指導は、月・水・金・土曜日の診療日に実施しています。
午前 9:00~12:00
午後14:00~15:00 ※土曜日は午前のみ
◇ 初回は1回30分程度、2回目以降は約20分程度行います。予約が必要です。
担当の医師にご相談ください。
地域の先生方からご依頼を受け、当院の管理栄養士が外来栄養食事指導を行います。
外来栄養指導をご希望の場合は、医療連携室までお問い合わせください。